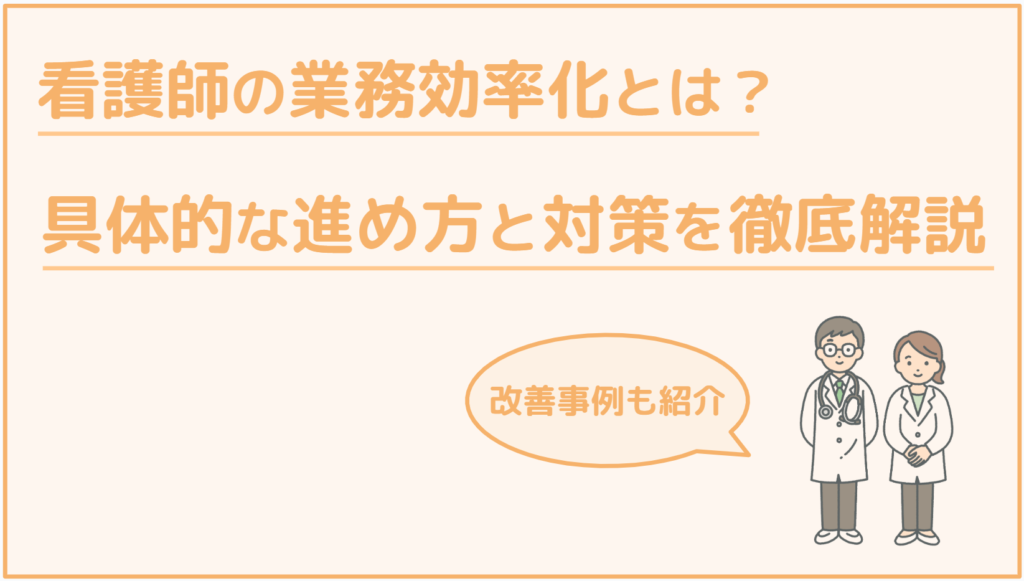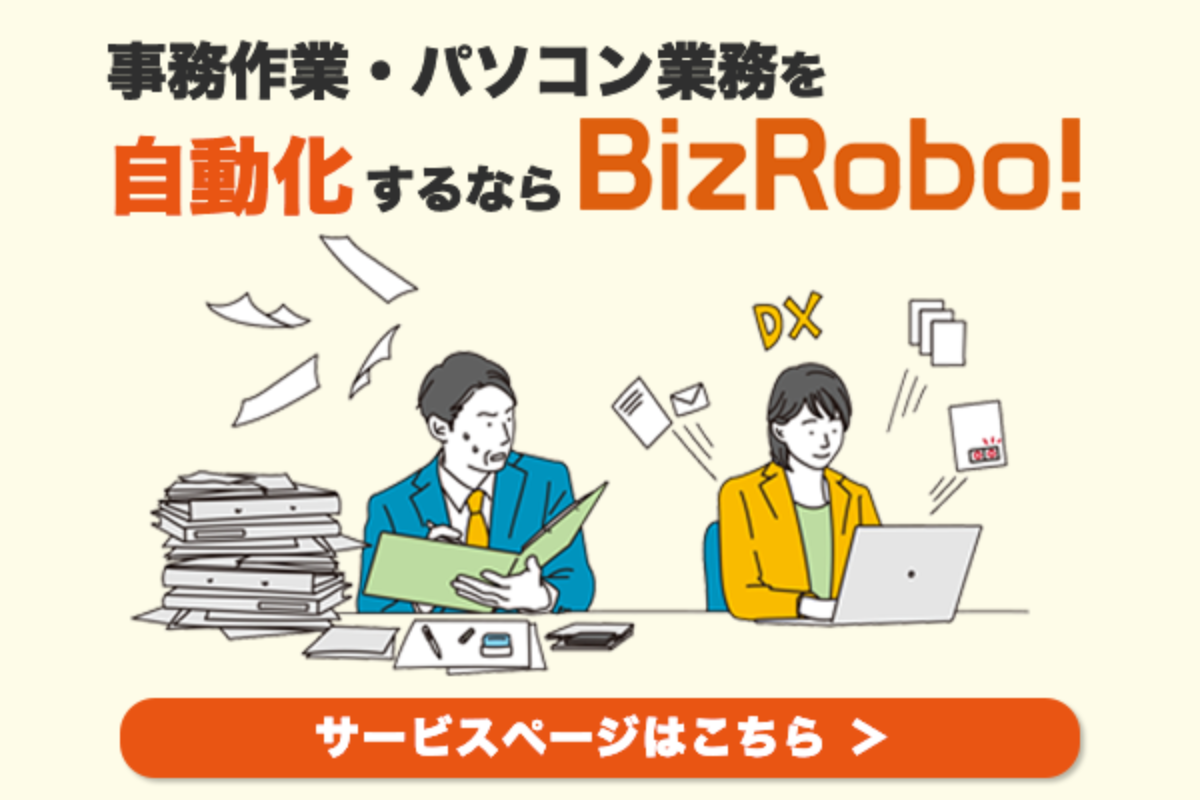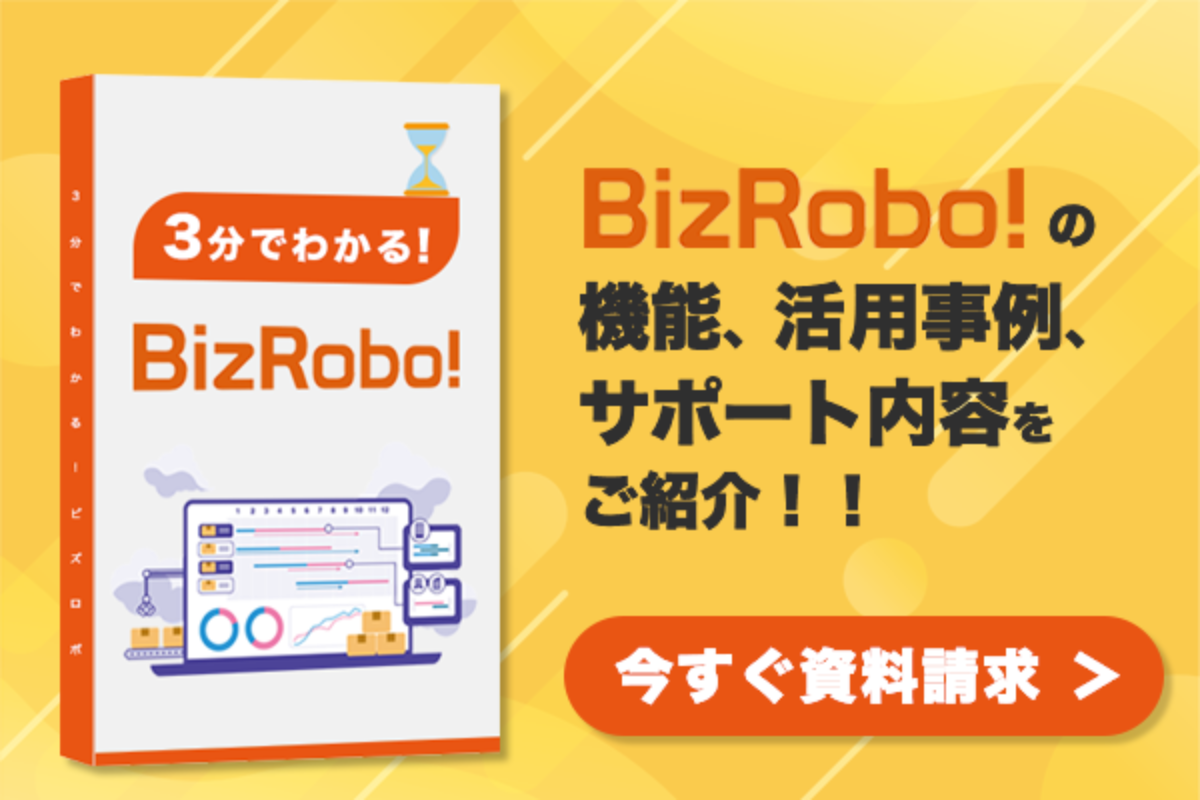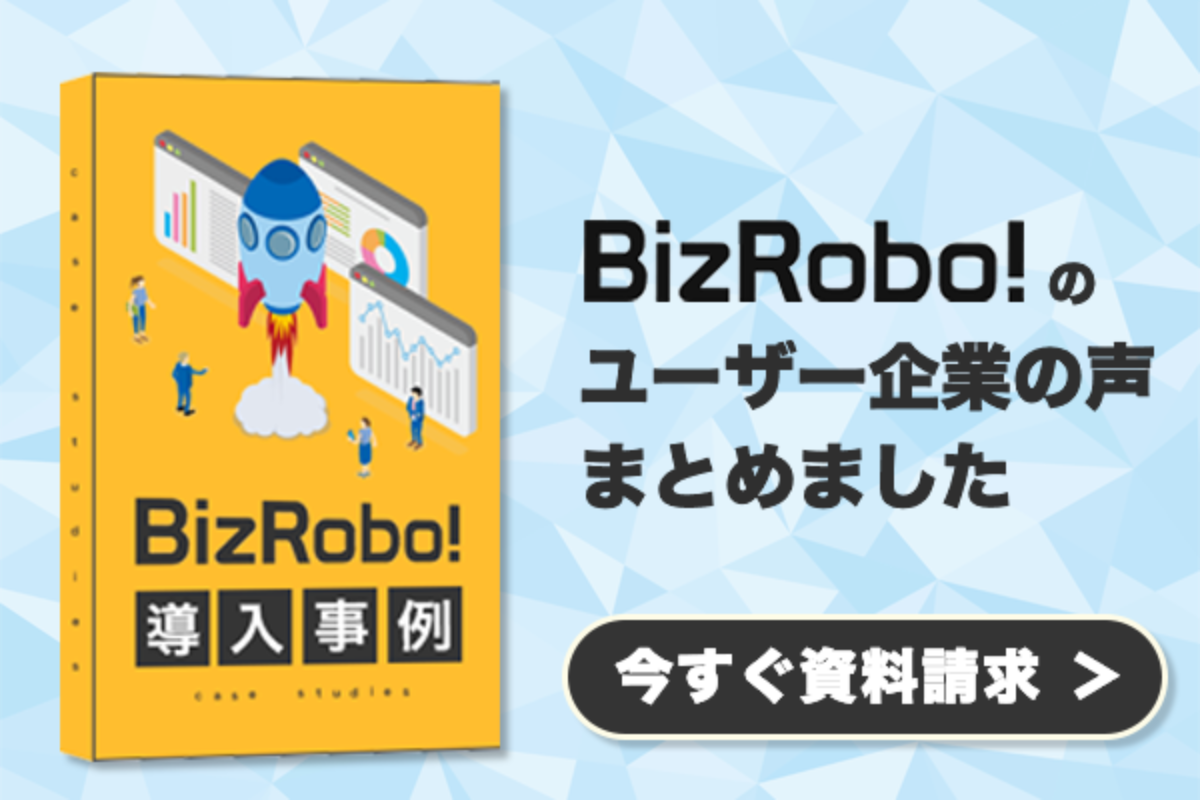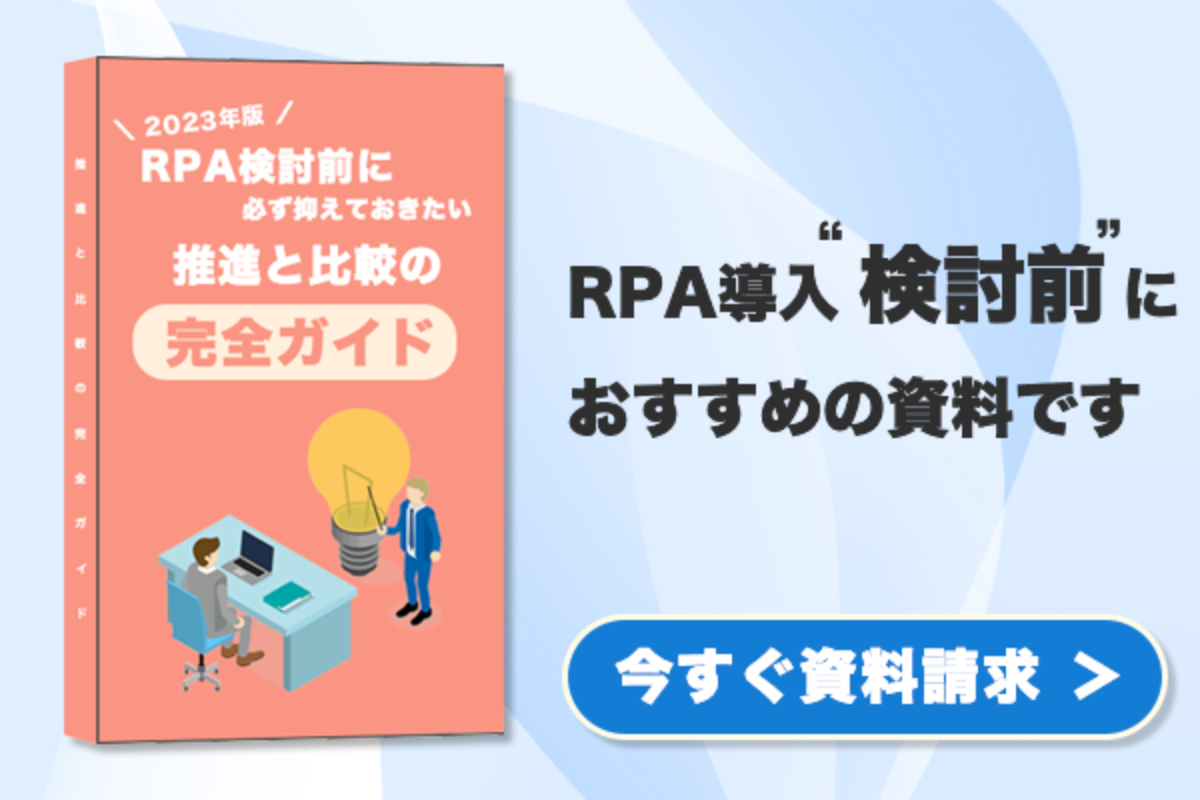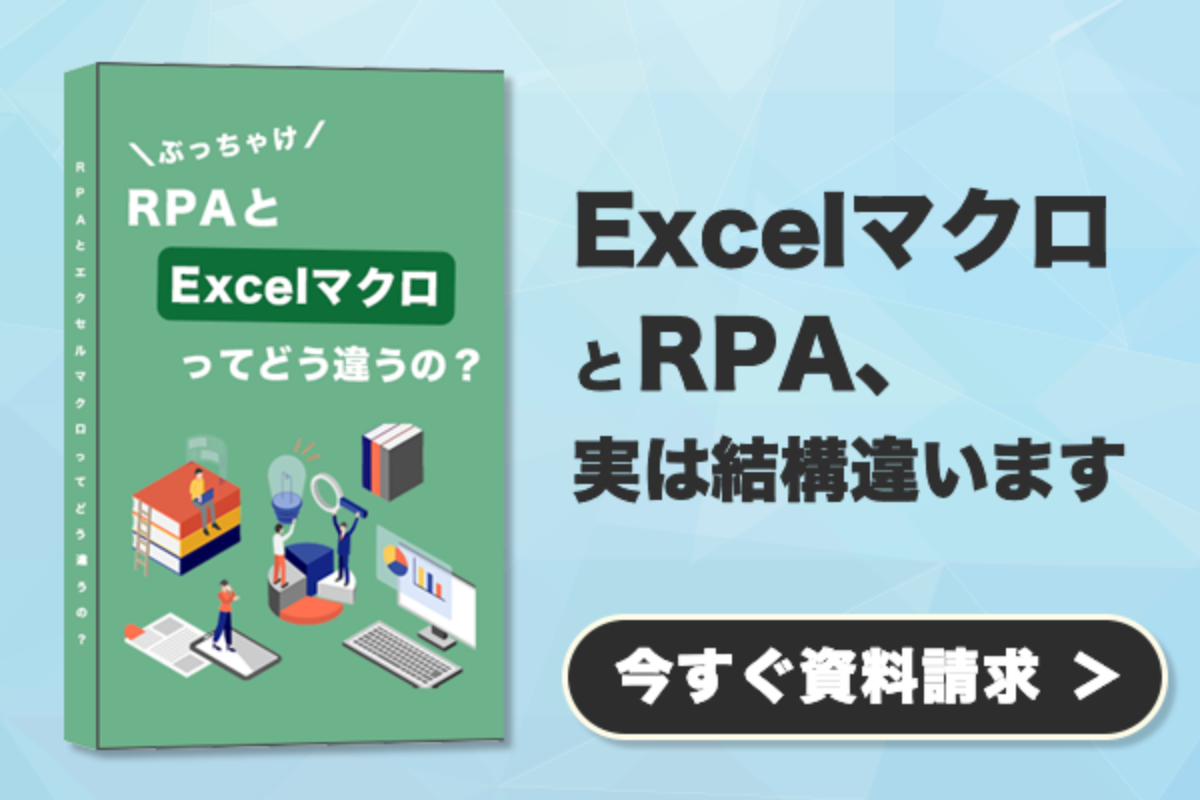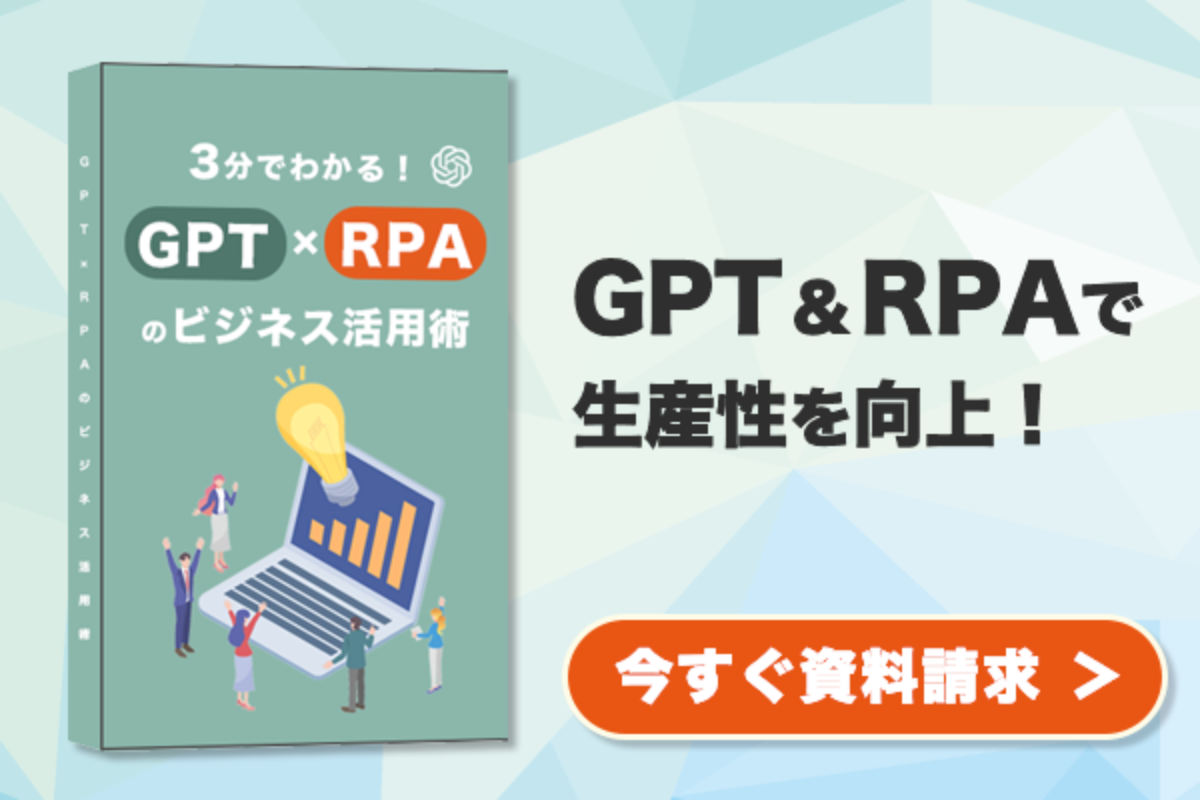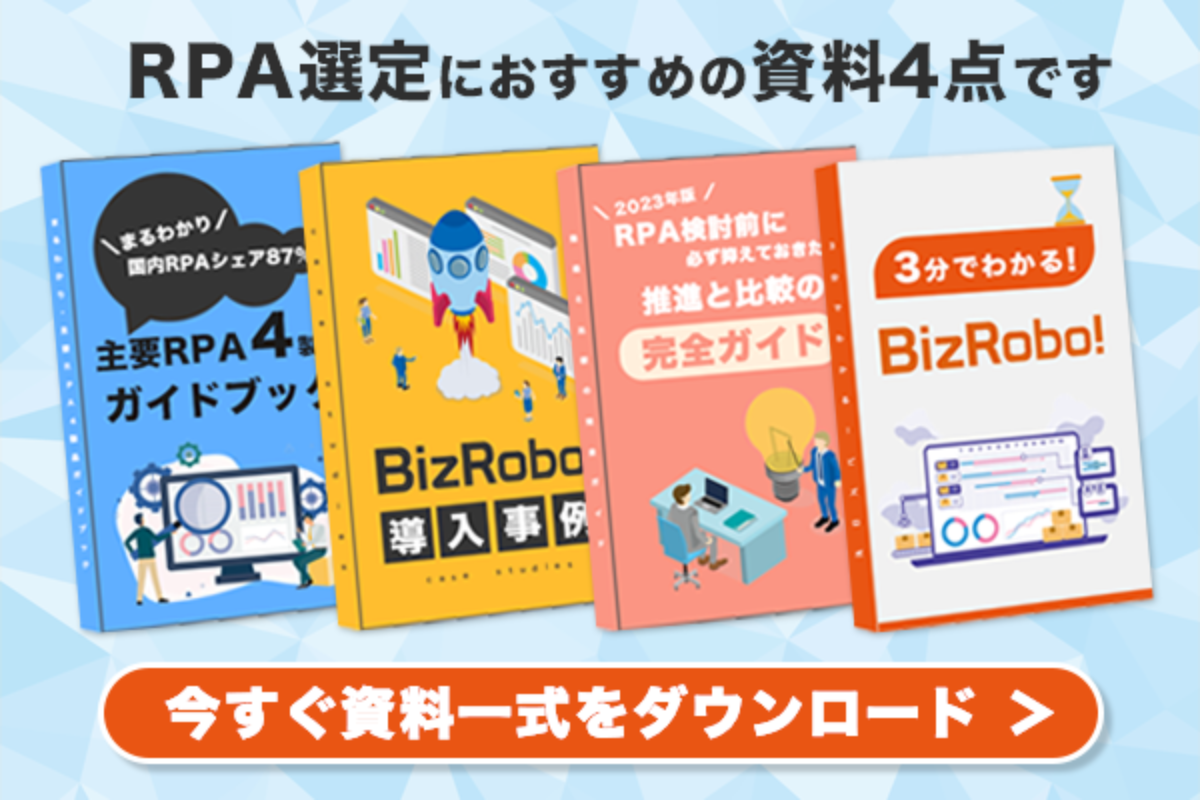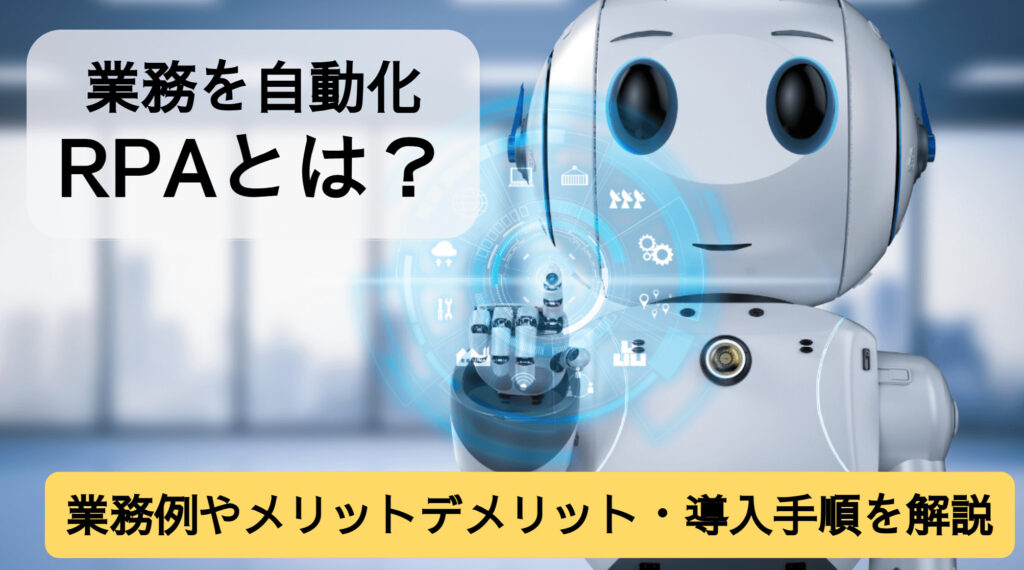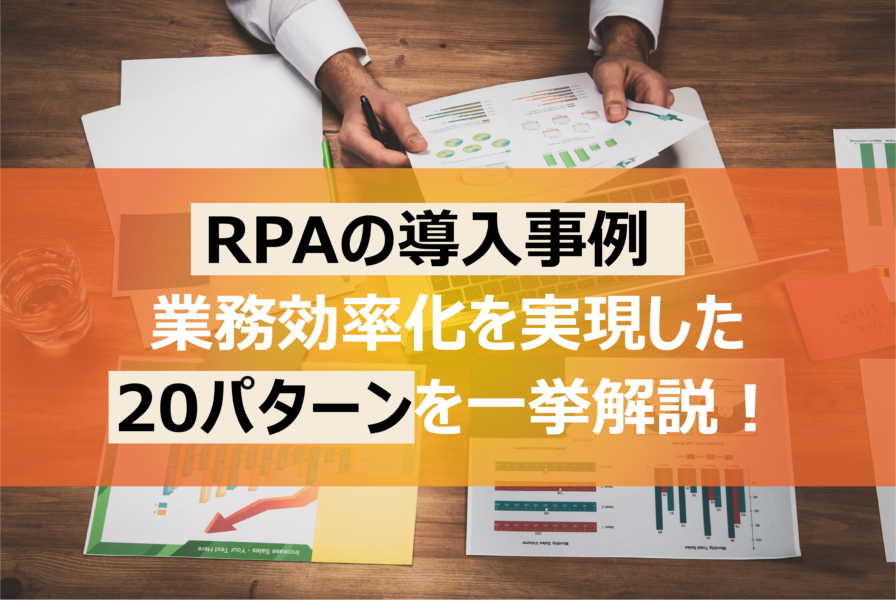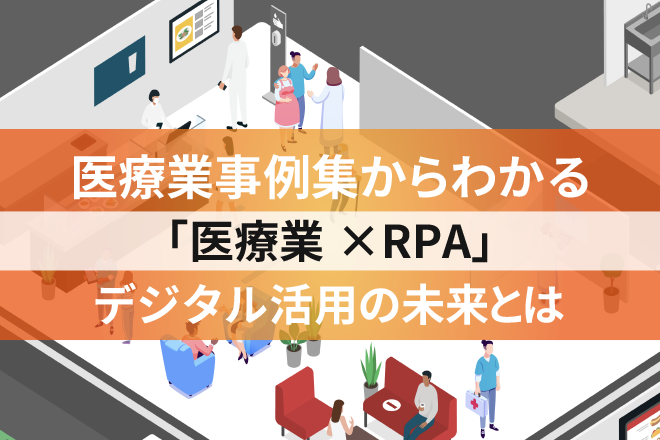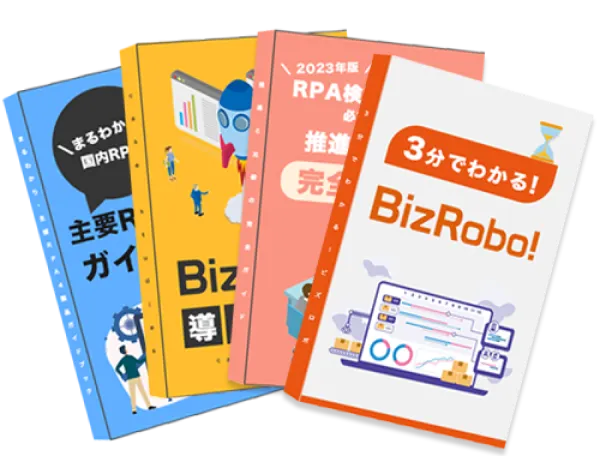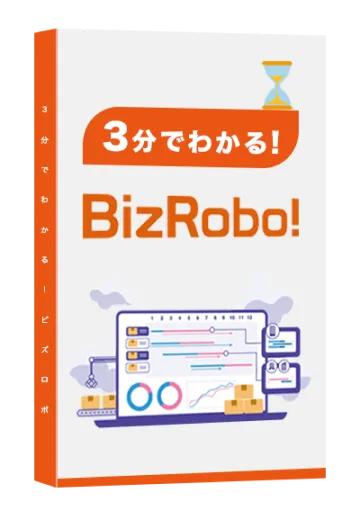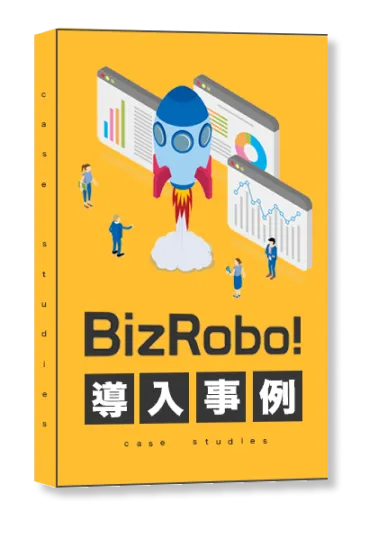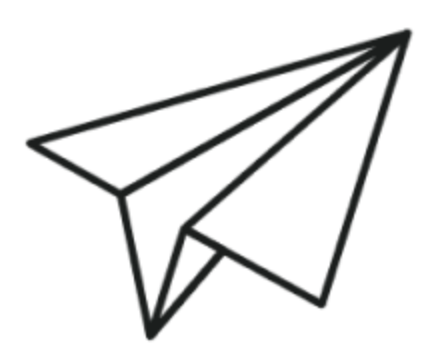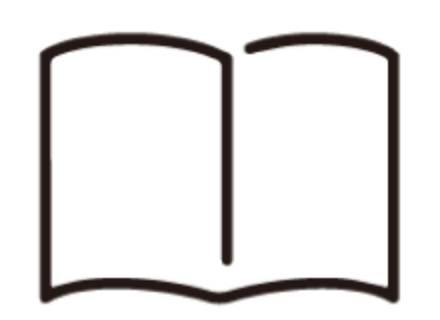BizRobo! ブログRPA関連のお役立ち情報をお届けします
「業務効率化に成功した企業の事例を知りたい」
「業務効率化につながるツールの種類や費用について知りたい」
業務の効率化や、コストカット、働き方改革への対応を検討中で、このようなお悩みの方はいませんか?
効率化の手段はさまざまですが、結論からいうと、どんな企業であっても導入しやすいRPAツールがおすすめです。
今回は、業務効率化の成功事例や、RPAツールの導入事例をあわせて10個紹介します。また、業務を効率化するメリットや必要なステップ、おすすめのRPAツールについても解説。
この記事を読めば、どのように業務を効率化していけばいいのか、具体的な道筋がしっかりと掴めるようになります。
目次
業務効率化に成功した企業の事例10選
ここでは、さまざまな施策により業務効率化に成功した事例を10個取り上げて解説します。
バリエーション豊富な業種・業界・事業規模の事例を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
完全週休3日制を目標に掲げることで従業員の意識を変革
戸建住宅の分譲販売を行っている株式会社建新では、「ALL-Win」を企業理念として掲げ、残業時間削減と完全週休3日制移行を目指して働き方改革を推進しています。
2020年6月からは月の平均残業時間を40時間未満にする具体的目標を設定し、次のような施策を行いました。
残業時間削減&完全週休3日制に向けた取り組み
- ・月に1度の週休3日制をトライアル導入
- ・始業5分前にPCの電源をオン・就業5分後にはオフにする自動制御の導入
- ・残業を前日までに上司に申し出る事前申請制の導入
- ・労働時間の日次・週次モニタリングを実施
- ・現場管理ツールのデジタル化
これらの施策により、2019年度には1人あたり月平均40時間であった残業時間は、2021年には約20時間にまで減少。営業利益は2020年度から2021年度で約200%上昇したほか、新卒採用募集も9倍に増加しました。
残業時間の削減や完全週休3日制といった、従業員にとってもメリットの大きい目標を掲げることで、会社・従業員が一体となって業務効率化に取り組んだ好例といえるでしょう。(※1)
テレワークの推進で通勤負担の軽減&モチベーションの向上
ネットワークソリューション事業を行っているNECネッツアイ株式会社では、テレワークの推進により業務効率化・生産性向上を実現しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により注目度が高まったテレワークですが、NECネッツアイ株式会社では2007年からペーパーレス化の推進、2015年1月からテレワークの実証実験を行うなど、先進的な取り組みを行っていました。
テレワークへの移行に向けた歩み
- ・ペーパーレス化の推進
- ・フリーアドレス制の導入
- ・1日単位での在宅勤務の実証実験
- ・業務の進捗や成果、残業時間を管理できるツールの開発
- ・サテライトオフィスの開設
- ・全従業員を対象にしたテレワークの本格運用
テレワークへの移行にあたっては、前もってペーパーレス化を行ったり、段階ごとに検証を重ねたりすることで、現場の意見や実験結果を取り入れながら着実に実現したことが分かります。(※2)
情報の共有・マニュアル化で業務の効率化&均一化
インターネット上で農機のマーケットプレイスを運営している株式会社唐沢農機サービスの事例です。
同社の顧客層は主に中高年層であり、若い世代のスタッフは10年以上昔の機材に対する問い合わせなどに対応できず、一旦保留としたのちに詳しいスタッフに相談し、折り返し連絡することが多かったそうです。
そこで、属人化していた情報を共有化・マニュアル化することで、業務の効率化と均一化を図り、スピーディーな顧客対応を実現しました。
業務のマニュアル化による効果
- ・スピーディーかつ的確な顧客対応の実現
- ・月平均約20時間の残業時間が平均8時間に短縮
- ・未経験者やパート従業員でも雇用しやすくなった
業務のマニュアル化は、業務効率化につながるだけではなく、顧客・従業員の双方にメリットをもたらす施策といえます。(※3)
クラウドシステム・チャットツールの導入で情報共有の効率化
ソフトウェア開発を行っている株式会社永和システムマネジメントは、クラウドシステムやチャットツールを活用することで、業務効率化・ワークライフバランスの向上・優秀な人材の確保に成功しています。
福井県福井市に本社を置く同社では、東日本大震災をきっかけに在宅勤務のトライアルを実施し、2012年8月から本格的にテレワーク制度を導入しました。
テレワーク環境でも生産性や品質を落とさず、また、多様な働き方を受け入れるために、次のような施策を実施しています。
テレワーク環境での生産性を向上させる仕組み
- ・ドキュメントやスプレッドシートを共有・同時編集するためにGoogle Workspaceを導入
- ・勤務開始・休憩・終了をリアルタイムに共有できるチャットツールを自社開発
- ・Web会議システムを導入し、遠隔地間でのミーティングに活用
これらの施策により生産性が向上した結果、従来は『残業は美徳』とさえ思われていた社内の雰囲気が変わり、現在は1ヶ月平均16時間程度で推移しています。
また、多様な働き方が可能となったことで、本社出勤が難しい従業員を積極的に雇用できるようになり、従業員の退職・人材の確保にもつながっています。(※4)
バックオフィス業務のIT化で長時間労働の縮減&ミス防止
設備メンテナンスを行う有限会社タイムカンパニーでは、『経営者が経営に専念できる環境を整える』という観点から改革をスタートし、結果として会社全体の負担軽減や生産性向上にもつながりました。
同社では、代表取締役が自ら会社の管理部門を担当しており、経理などの事務作業に時間を取られてしまい、本来の基幹業務に注力できる環境ではありませんでした。
そこで実行したのが、以下の施策です。
経営者が経営に専念できる環境づくり=会社全体の業務効率化
- ・総務担当者を雇用
- ・総務業務に関する業務効率化ツールの導入
- ・クラウド型給与計算システムの導入
- ・勤怠管理システムの導入
このように、連鎖的にIT化・クラウド化を推進したことで、最終的にはバックオフィス業務全体の効率化や、従業員の利便性向上といった結果がもたらされました。
業務効率化を検討するとき、遠いところに目標を置くと、どこから手をつけたらいいか分からなくなってしまうことがあります。
そのため、まずは目先の困りごとを解決する方法から考えてみるとよいでしょう。(※5)
従業員との業績共有で社員の意識改革&生産性向上
製造業など、出社・手作業による業務が前提となる業種の場合、テレワークの導入やクラウド化などには限界があります。
自動化機械装置の設計・製作を行っている株式会社アイダメカシステムでは、従業員の声に耳を傾け、一人ひとりの裁量を大きくすることで意識変革を行い、生産性の向上に成功しました。
従業員目線に立った生産性向上の仕組み
- ・個人面談の実施
- ・会社業績を従業員と共有
- ・完全週休二日制の導入
- ・年次有給休暇の時間単位取得
- ・社員の自立性の尊重
- ・オンライン目安箱の設置
特に注目すべき点としては、会社業績の共有が挙げられます。
面談時に会社業績の試算表を参照し、「長時間働き、頑張っている」という実感が必ずしも会社の利益につながっていない事実を従業員と共有することで、従業員ひとりひとりが経営者に近い視点に立って仕事に向き合うようになりました。
また、業務のなかで気づいたことや改善点、要望などを匿名で投稿できるオンライン目安箱を設け、問題点にいち早く対応できる体制を整えました。
これらの施策は、IT化が難しい業種や予算をかけづらい中小企業・スタートアップ企業でも導入しやすいため、最初に行う業務効率化施策としてもおすすめです。(※6)
ICT化と専門スタッフの雇用で業務負担を軽減
認定こども園や児童館などの運営を行っている社会福祉法人育和会では、ICTシステムの導入と、専門スタッフの雇用により、保育士の負担を軽減し、業務効率化を実現しています。
労働時間削減と業務負担軽減のため行った施策
- ・ICTシステムを導入し、保育関連事務作業の負担軽減
- ・PCやタブレット端末の複数台導入
- ・専門スタッフの雇用
ICTシステムの導入により、欠席連絡や検温チェック、連絡帳、お知らせの一斉配信、アンケート、写真販売、献立表、指導案など、複数の業務を一挙に効率化することができました。
また、職員用のPCやタブレット端末を複数台導入したことで、同時に複数人が作業に取り掛かれる環境を構築しました。
さらに、清掃や食事の配膳など、保育以外に関する業務について専門スタッフを雇用したことで、保育士の業務負担軽減も実現しています。
効率性が求められるデジタル化可能な部分と、人の目や感覚で確認するべきアナログな部分を見極め、それぞれに対応する施策を組み合わせるという姿勢は、どのような業種・業界であっても参考になる施策といえるでしょう。(※7)
ペーパーレス化で業務効率と決裁スピードを向上
機械部品や工作機械などの卸売・小売を行っている疋田産業株式会社では、社内の決裁フローのペーパレス化により、業務効率化の向上と入力ミスの削減に取り組んでいます。
ペーパーレス化のメリットは以下の通りです。
- ・稟議から決裁までのスピードが高まる
- ・遠隔地であっても即座に確認できる
- ・どこでフローが止まっているのか確認できる
- ・印刷・封入・配布などの作業が不要になる
- ・情報の保存・管理が容易である
- ・内部統制を強化できる
決裁フローの電子化により、いつでも・どこでも社内文書を確認できるという点から、リモートワークや時差出勤など多様な働き方に対応しやすくなるというメリットも挙げられます。
近年は、民間企業のみならず行政や地方自治体でも電子決裁システムを導入するケースが増えており、国が脱ハンコ社会を進めていることからも、今後ますます電子化の流れは加速していくでしょう。(※8)
ノルマを課さず目的意識を共有することで27期連続で売上増
主にリサイクルトナーの販売などを行っている株式会社セラビでは、あえて営業ノルマを課さず、従業員が自発的に成績を出せる仕組みを構築することで、業務の効率化と売上の増加を実現しています。
ノルマなしでも27期連続で売上高増を実現したメソッド
- ・経営者を含む社内全体が所定労働時間内に業務を終わらせる風土をつくる
- ・年度当初に各自の目標を定める
- ・どうしたら目標を達成できるかチームで考える
- ・結果を出した人が昇進・昇給できる仕組みを整える
- ・営業エリアを定期的に見直し属人化を防ぐ
営業部門へのノルマ設定は、高すぎても低すぎても従業員のモチベーション低下につながる可能性があり、また、設定作業自体にも時間と労力が必要となります。
とはいえ、目標となる指針が全くないとなれば、それはそれでモチベーションの維持は難しいでしょう。
そこで同社では、個々のノルマを各自・チームで検討させることとし、成果主義の導入や原則残業禁止といったバックグラウンドを整備することで、自発的な業務効率化・労働時間短縮を促すことに成功しています。
その結果、月平均残業時間0.16時間、年次有給休暇取得率9割超、創業以来27期連続売上増という、驚異的な成果につながりました。(※9)
1分単位のデータ管理で時間外労働を月12時間削減
ロボティクスソリューション事業などを手がける株式会社ミスズ工業では、個人の成長が会社の成長・会社の成長が社会の成長という経営理念を掲げ、経営側と従業員側が一体となって業務効率化に取り組んでいます。
従業員と会社それぞれの成長を促す施策
- ・個人ごとの残業データを1分単位で管理、グラフ化
- ・全従業員を対象としたフレックスタイム制の導入
- ・年次有給休暇取得の促進と取得状況のデータ管理
- ・勤続年数に応じたリフレッシュ休暇の導入
- ・育児短時間勤務制度の自発的拡充(法定は3歳未満→同社では小学校就学まで)
- ・全従業員を対象とした中長期育成計画の作成
残業時間や年次有給休暇の取得状況のデータ化・グラフ化は、比較的導入が簡単な施策でありながらも、本人や管理職にとっては視覚的に情報を確認できるという点において、意識変革をもたらしやすい有効な手段です。
また、会社の成長という観点だけではなく、従業員の成長を促し個々の能力を高めることで、結果として会社全体の生産性向上につながるという観点も、同社から学ぶべき考え方といえるでしょう。(※10)
業務効率化がもたらすメリット5つ
ここまでは、業務効率化に成功した企業の実例を取り上げ、各企業にどのような効果をもたらしたのかを紹介しました。
以下からは、業務効率化により得られる効果を一般化し、効率化の主なメリットを5つ取り上げて解説します。
メリット1.コスト削減
業務効率化で最も直接的に得られるメリットとしては、コストの削減が挙げられます。
無駄なプロセスや重複する作業を排除し、業務を最適化することで、リソースの無駄遣いを防ぐことが可能です。
例えば、これまで手動で行われていたデータ入力作業を自動化ツールに置き換えることで、人的リソースの削減や、労働時間の削減につながるでしょう。
また、効率化によって生産性が向上すれば、短時間での成果達成が可能となるため、長期的な経費も節約できます。
このように、業務効率化は短期的なコスト削減を実現できるだけではなく、企業の持続可能な成長を促すという観点からも、重要な戦略として機能するのです。
メリット2.利益の増大
業務効率化により生産性が向上すれば、売上の増加にもつながります。
これは、効率化によって従業員が本来の業務や、より生産性の高い業務に集中できる時間が増えるため、付加価値の高い仕事に取り組むことが可能となるからです。
また、生産ラインの効率化による生産スピード向上、顧客対応の迅速化による顧客満足度の向上など、業務効率化自体が売上の増加に直結するパターンもあります。
コスト削減効果と相まって、効率化の成果は純利益の増大としても企業の財務状況に反映されます。
すなわち、業務効率化は企業の収益性を高めるための不可欠な手段といえるのです。
メリット3.従業員のモチベーション向上
業務効率化は従業員のモチベーション向上にも大きな影響を与えます。
効率的な業務環境が整うと、従業員は不必要なストレスから解放され、より生産的に仕事を進めることができるようになります。
面倒な手続きや冗長な報告書作成といった業務が減ると、従業員は本来の業務に集中できる時間が増え、達成感や仕事への満足感が高まるため、モチベーションの向上を期待できます。
また、効率化によって生まれる余裕時間を利用して、従業員のスキルアップやキャリア開発に充てることも可能です。
企業が従業員の成長をサポートすることで、従業員の勤労意欲や積極性が高まり、離職率の低下にもつながるでしょう。
メリット4.人材不足の解消
業務効率化は、人材不足という難しい課題を解決するための有効な手段ともなります。
効率化により、一人ひとりの従業員がより多くの仕事こなせるようになれば、少ない人数でも高い生産性を維持できます。
例えば、ITツールの導入により、従業員が行っていた反復的な作業を自動化し、より重要な業務に集中させたり、スキルが低い従業員であっても高品質な業務を行えたりするようになります。
また、効率化によって余裕が生まれた人員を新規プロジェクトに振り分けることで、企業の成長戦略に柔軟に対応することも可能です。
さらに、業務効率化の過程で柔軟な働き方に対応できるようになれば、従業員の満足度が高まり、離職率の低下にもつながります。
メリット5.多様な働き方への対応
業務効率化は、多様な働き方への対応を可能にします。
リモートワークやフレックスタイム制など、柔軟な働き方を支援するためには、効率的な業務プロセスが不可欠です。
具体的には、クラウドベースのコミュニケーションツールやデータ共有プラットフォームを導入することで、場所や時間に縛られない働き方を実現できます。
これにより、従業員は自分に最適な環境で仕事ができるため、ワークライフバランスが向上し、働きやすさが増します。
特に、国際的なプロジェクトを抱えている企業にとっては、オンラインミーティングの実現やオンライン決裁システムの導入などは、もはや不可欠な施策といえるでしょう。
業務効率化にはRPAの導入がおすすめ
効率化の効果を最大化するためには、業務効率化の目的や、自社の業種・業界に合ったツールを選ばなければなりません。
ところが業務効率化には、特別な機材が必要になるものから意識改革まで、さまざまな方法があるため、どこから手をつけたらいいかお悩みの方も多いでしょう。
そこでおすすめしたいのが、RPAを用いた方法です。
以下からは、RPAの概要やDXとの違い、RPAの導入におすすめな業種・おすすめできない業種について詳しく解説します。
そもそもRPAとは?
RPA(Robotic Process Automation)とは、ソフトウェアロボットを用いて、ルーチンワークや定型業務を自動化する技術のことです。
例えば、データ入力や集計、定型的なメール送信などの繰り返し作業をプログラムによって自動化することで、人間が行う必要のない単純作業が減り、効率的な業務運営が可能となります。
『ソフトウェアロボット』というと難しく思われるかもしれませんが、RPAはプログラミングの知識がなくても操作できるツールが多く、ユーザーフレンドリーな設計がされているため、安心して利用できます。
RPAは従来の業務プロセスをそのまま模倣する形で導入できるため、既存のシステムやプロセスに大きな変更を加えることなく、自動化を実現できる点も大きな強みです。
RPAを導入することで、人的ミスの削減、作業スピードの向上、さらにはコスト削減や業務の透明性向上も期待できます
関連記事:RPA(ロボティックプロセスオートメーション)とは
RPAとDXの違い
RPAとDX(デジタルトランスフォーメーション)は、しばしば混同されがちですが、両者には目的・範囲に大きな違いがあります。
RPAとは特定の定型業務を自動化する技術であり、業務プロセスの一部を効率化することに重点を置いている一方、DXは企業全体のデジタル化を推進し、ビジネスモデルそのものを変革する広範な取り組みです。
DXの具体例としては、新しいデジタル技術を活用して、製品やサービス、顧客体験を向上させるとともに、組織文化やプロセス全体を再構築することなどが挙げられます。
また、両者は相反する概念ではないため、企業全体の戦略的な改革を目指していく(DX)なかの、そのひとつの手段として定形業務の自動化する(RPA)といった状況もありえます。
RPAに向いている業務・向いていない業務
RPAは多くの業務の効率化に役立ちますが、あらゆる業務を自動化できるわけではありません。
一般的に、RPAは、繰り返しが多く・ルールが明確であり・変化が少ない業務の代替に向いており、逆に、創造性や判断力が求められる業務や、例外対応が多い業務などの代替には向いていません。
| RPAに向いている業務 |
| ・データ入力 ・請求書の処理 ・在庫管理 ・給与計算 ・顧客データ管理 ・メール自動送信 ・注文処理 |
| RPAに向いていない業務 |
| ・戦略的意思決定 ・創造的業務 ・顧客との直接コミュニケーション、交渉業務 ・例外処理 ・変化が多いプロセス |
このように、RPAにより代替不可能な業務も存在するため、RPAの導入を検討する際には、自社のニーズをしっかりと把握し、どのプロセスが自動化に適しているかを慎重に判断する必要があります。
関連記事:RPAができることは?できないことや導入事例・注目される理由も解説
RPA導入による業務効率化の事例3選
RPAの活用によりさまざまな提携業務を自動化できれば、事業の効率化につながります。
とはいえ、RPAによりどのような業務を自動化できるのか、自動化によりどのような結果がもたらされるのか、イメージが湧かないという方もいるのではないでしょうか。
そこで以下からは、RPAを導入し、業務効率化に成功した企業の実例を3つ紹介します。
【製造】製造・流通・販売部門での稼働で年間6700時間の効率化を達成
無添加化粧品などの製造販売を手掛ける株式会社ファンケルでは、販売管理部門から「人が介在する定型作業を減らしたい」という相談を受け、RPAツール『BizRobo! Basic』を導入しました。
現在は23部門で約200体のロボットが稼働し、売上データの抽出や自社システムへの登録などを自動実行しており、年間約6,700時間相当の人的リソース創出に成功しています。
また、RPAツールの導入により創出できたリソースを活かして社内教育プログラムを拡充したことで、自社でRPAを設計・管理できるようになり、新たにRPAを活用する部署が広がっているといいます。
【サービス】3万会員分の大規模処理でバックオフィス業務の負担を大幅軽減
不動産情報サイトや不動産業務総合支援サイトの運営を行うアットホーム株式会社は、バックオフィス業務の負担軽減を目的に、RPAツール『BizRobo! 』を導入。
導入直後に3万会員分の大規模処理を短期間で乗り切り、社内表彰を獲得したことでRPA活用の取り組みは全社に広がり、社内でのRPA活用が促進されました。
また、AI-OCR製品を導入して『BizRobo! 』と連携させたことで、営業部門が受領した紙媒体申込書と受注登録システムの自動突合作業が可能になり、ダブルチェックの手間を削減し、作業員の精神的負担も軽減しました。
これらの施策により、同社では約80体のロボットが定常稼働し、月間約400時間の時間削減効果を達成しています。
【卸売・小売】専門スタッフ2名体制で各部門80〜99%の時間削減
全国で生活雑貨販売店を展開している株式会社ロフトの事例です。
かねてから事務作業効率化のためにマニュアルの作成や作業の集約、手書き管理をExcelでの管理に置き換えるなどの施策を行っていましたが、手動入力による時間のかかる作業や、ミスの多さが課題となっていました。
そこでRPAツール『BizRobo! 』を導入し、AI-OCR製品も活用して請求書処理業務を中心に運用を開始したところ、処理スピードの向上・入力ミスが減少し、最初の1年だけでも年間6,000〜7,000時間の削減効果を創出しました。
次第に他部署からもRPA化の要望が寄せられたため、同社ではRPA推進チームを発足して専任スタッフを設置。
その結果、2020年7月時点では187体のロボットが稼働しており、月間3,650時間の削減効果を達成しています。
RPAで業務を効率化するならBizRobo! がおすすめ
現在はさまざまなRPAツールが登場していますが、導入が容易で費用対効果が高く、導入実績が豊富なRPAツールを探している方には『BizRobo! 』がおすすめです。
以下からは、『BizRobo! 』のおすすめポイントを3つに絞り、具体的に紹介していきます。
BizRobo! の魅力①:サポートコンテンツが充実している
『BizRobo! 』では、RPAの導入に失敗してしまいやすい、立ち上げ・人材育成・運用という各ポイントごとに手厚いサポートを提供しているため、はじめてRPAを導入する方でも安心してご利用いただけます。
まず、豊富な導入実績を活かした立ち上げサポートで、自動化業務の洗い出しから導入要件の検証まで徹底的に支援します。
立ち上げ後は、豊富な動画コンテンツで体系的に学べる『BizRobo! eラーニング』や、情報検索サイトの『ナレッジベース』、ユーザーコミュニティなどのツールで、誰でも簡単に開発スキルを向上させることが可能です。
さらに、個別伴走サポートでは、メールや電話での対応に加え、チャットサポートを受けられるため、不明点があってもすぐに改善することができます。
長期にわたって安心してご利用いただける体制が整っているからこそ、販売開始から15年が経った今でも、継続率は99%以上となっております。
BizRobo! の魅力②:インストール数に制限がなくライセンスコストが一律で安心
『BizRobo! 』ではインストール数に制限を設けていないため、一律のライセンスコストでご利用いただけます。
他のRPAツールでは、ロボットを作るたびに追加のPCやライセンスが必要となり、想定していた費用対価を得られないことも少なくありません。
しかし『BizRobo! 』なら、開発者が増えてもライセンスコストが増加する心配はなく、むしろロボットを増やせば増やすほど費用対効果が高まる料金体系となっています。
ロボットの数が増えても、ロボットやユーザーを一元管理できるため統制のとれたプロジェクト進行が可能であり、リモートでもご利用いただけるため、多様な働き方に対応可能です。
BizRobo! の魅力③:1ヶ月の無料トライアルで自社に合うかを試せる
『BizRobo! 』では、1ヶ月の無料トライアルをご提供しており、サポートコンテンツも含めて全て無料でご利用いただけます。
RPA導入による費用対効果の測定にご利用いただけるのはもちろんのこと、インターフェースの使い勝手やサポートコンテンツの充実具合など、30日間しっかりと検討してご利用を開始できるため安心です。
ぜひ30日間無料トライアルのご活用で、『BizRobo! 』がどのように業務を効率化しコストを削減するのかを体験し、その効果を実感してください。
まとめ|RPAツールBizRobo! の導入で業務効率化を実現しよう
業務効率化にはさまざまな方法があり、自社にあった方法を見つけるためには、まず自社の課題を洗い出したうえ、他社の成功事例を学びながら慎重に施策を実施していく必要があります。
具体的な業務効率化手法のなかでも、比較的どのような業種・業界でも導入しやすく、費用対効果の高い方法としてRPAツールの導入がおすすめです。
RPAを導入すれば、例えばデータ入力や注文処理などの定型業務を自動化でき、人的・時間的リソースの削減を実現できるため、より生産性の高い業務に注力できます。
RPAツール『BizRobo! 』は、長年の経験にもとづき導入・人材育成・運用をサポートしているため、はじめてRPAを導入する方でも安心・簡単にご利用いただけます。
また、導入後もライセンスコストを一律でご利用いただけるほか、30日間の無料トライアルもご利用いただけるため、費用対効果の面からも高く評価されています。
業務効率化のために何から手をつけたらいいか分からないという方や、RPAツールの導入を検討している方は、ぜひ『BizRobo! 』無料トライアルをご活用ください。
【参考】
※3 「株式会社唐沢農機サービスの事例」(厚生労働省)(https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/casestudy/file142/)を加工して作成
※4 株式会社永和システムマネジメント|働き方・休み方改善ポータルサイト
※5 「株式会社唐沢農機サービスの事例」(厚生労働省)(https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/casestudy/file155/)を加工して作成
※6 働き方・休み方改革 企業事例|働き方・休み方改善ポータルサイト
※10 「株式会社ミスズ工業の事例」(厚生労働省)(https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/casestudy/file106/)を加工して作成



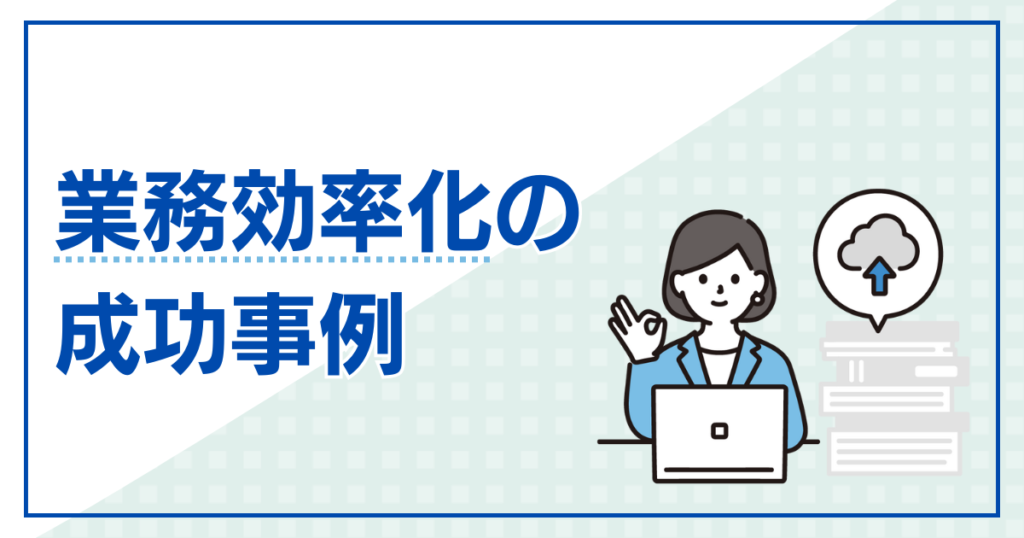
 いいね 0
いいね 0